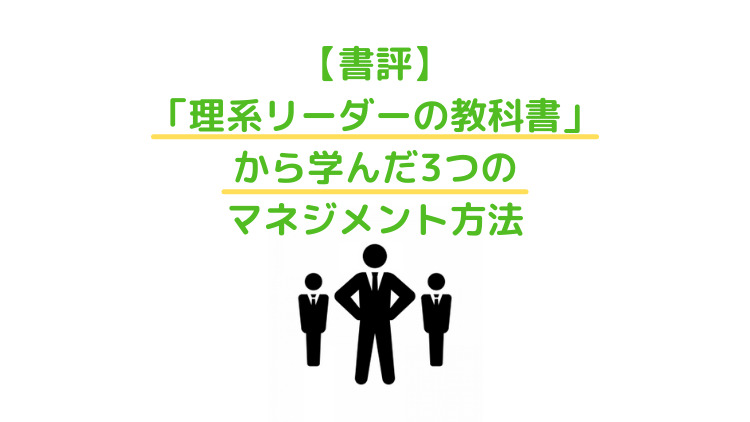理系リーダーはメンバーの技術的仕事内容にも精通しているはずです。
科学・技術的な面で現状把握にバイアスがかかってないかチェックしましょう。
実践例:プロセスのチェック
案件をスケジュール通り終えるためにプロセスのチェックは重要です。
私は、プロセスのチェックポイントとして3つを重視しています。
ポイント
- そのプロセスで課題を解決できるのか?他の方法はないか?
- スケジュールは適切か?必要な資源は十分か?
- プロセスが計画通りに進んでいるかどうかのチェックはどのように行うか?
メンバーが作った作業計画が、課題解決につながるかを確認しましょう。
もし、より良い方法があるのであれば、担当者自身に考え直してもらうこと必要があります。
スケジュールは予想より遅れることがほとんどです。
リーダーは担当者が提出したスケジュールより、遅くなることを想定する必要があります。
また、必要な物資などの資源が足りているのかを確認することもリーダーの仕事です。
足りていないのであれば、リーダーの責任で確保する必要があります。
何をクリアすればゴールに近づいているといえるのかを確認することも重要です。
- 収率~%以上となれば、この工程はクリア
- 規格Aを工程Bでクリアすれば、ゴールに近づく
など、ゴールまでのチェックポイントをリーダーと担当者の間で明確にしておきましょう。
まとめ
研究開発職リーダーの重要な仕事は、チームメンバーのペースメーカーとして走るべき道をともに作り上げることです。
この記事で紹介した3つのポイントをを実践して以降、メンバーの成果の品質が高まり、スケジュールが後ろ倒しになりにくくなっています。
メーカー若手リーダーの方は是非参考にしてください。
この記事からわかること
- 理系若手リーダーが実践しているマネジメント手法
私(@okamotobiblio)はメーカー技術職として、入社4年次から3人チームのリーダーを務めています。
最初は思い通りにチームを率いることができず、多くの失敗をしました。
しかし、「理系リーダーの教科書」を読み、実践することで、チームとして成果を上げることができるようになってきました。
この記事では、リーダーとしての失敗を踏まえて、私が現在実践したポイント3点を紹介します。
この3点は、特にメーカーで働く若手リーダーにとって有用なポイントですので、研究開発職のリーダーの方は参考にしてください。
理系リーダーとして実践している3つのこと
私が理系リーダーの教科書を参考に、リーダーとして実践たことは以下の3つです。
- ルールを決める
- ゴール→現状→プロセスを明確にする
- チェックに時間を使う
この3つを実践することで、リーダーとして成果を上げることができるようになりました。
なぜこの3点が重要なのかを解説します。
リーダーとして失敗したこと
私は製造業研究職として新卒3年目の時に、チームのリーダーとして働くことになりました。
それまでの働きぶりを評価してもらってことだったのですが、初めはチームとして成果を上げることができませんでした。
チームメンバーに頼らず、すべての仕事を自分でやろうとしてしまったことが原因です。
チームリーダーの仕事には、
- メンバーの仕事の振り分け
- 実験操作の指導
- プロジェクトの進捗確認
- 取引先とのやり取り
- 社内報告、資料作成
- 自分の実験
などがあります。
これに加えて、メンバーにやってもらうべき仕事を自分でやろうとしてしまったため、仕事がパンクしてしまったのです。
確かに、自分でやった方が早く終わる仕事は多いです。
しかし、メンバーに仕事を与えず、自分で行ってしまうことには2つのデメリットがあります。
- 仕事の質が悪くなり、成果が上がらない
- メンバーが育たない
仕事の質が悪くなり、成果が上がらない
私自身がチームの構成員の一人であったときは、自分の頑張りで案件を進展させることできました。
しかし、実際にはリーダーは多くの案件に関わることになります。
メンバーがやるべき仕事をリーダーが行うと、その案件だけに集中することができないため、仕事の質が悪くなります。
チームメンバーが個々の担当する案件で成果を出せないと、チームとして成果を出せないのです。
メンバーが育たない
また、メンバーから仕事を取り上げると、結局そのメンバーが育ちません。
いつまで経っても、リーダーが最前線で業務をすることになり、チーム全体の成果が頭打ちになってしまいます。
当時、私にはリーダーとしての技術が足りないと実感しました。
そこでマネジメント関連の本を読み、試行錯誤した結果、3つのポイントを実践することが重要だと分かったのです。
リーダーの仕事はペースメーカーになること

リーダーの仕事とは何でしょうか。
例えば、以下の3点が思い浮かびます。
- ビジョンを示し、チームを良い方向に導くこと
- 仕事の先頭に立って、責任を引き受けること
- チームを鼓舞し、メンバーのモチベーションを上げること
いろいろなリーダー像があると思います。
私自身は表立って何かをやりたいという性格ではないですし、チームで成果を出すというよりは、自分の興味に赴くまま仕事をしたいと考えているタイプです。
人とのコミュニケーションもあまり得意ではありません。
つまり、私は一般的なリーダー像とは合致していない性格なのです。
メンバーをリードすることが苦手である私が実践できるリーダーシップとは何か?
そこで非常になった書籍が、「理系リーダーの教科書」です。
「理系リーダーの教科書」では、リーダーの仕事はペースメーカーであると主張しています。
「理系リーダーの教科書」はソニーのエンジニアとして活躍する著者が、理系の職場でのリーダーシップについて書いた本です。
理系リーダーは私の様に自己主張やコミュニケーションが苦手だったり、あるいはチームメンバーが一匹狼的であったりします。
この本では、そのようなチームの運営が具体的に、実践しやすい形で書かれています。
根底となるのが、リーダーはメンバーのペースメーカーであるという考え方です。
マラソンのペースメーカーは、設定タイム通りに走ることで、主役であるランナーたちが好記録を出す目の目印として役割を果たします。
リーダーもまた、主役であるメンバーたちが目標通りに仕事を終えることができるように目印を作ることが仕事なのです。
メンバーのペースメーカーであれば私でもできるのではないかと考え、実践しました。
ペースメーカーとして働くために重要なのが、先ほど紹介した3点なのです。
(1)ルールを決める
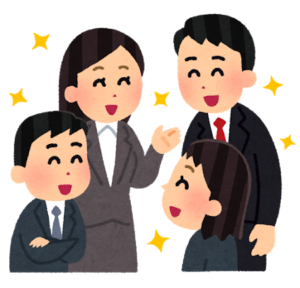
リーダーがペースメーカーとして振る舞うために重要なのことの1つ目は、メンバーとルールを決めることです。
特に理系職場のメンバーは自分の裁量で働きたい人が多いです。
一つ一つの作業を指示をしていると、リーダーはメンバーから支持してもらえません。
一方で、チームで成果を出すためにリーダーはメンバーをコントロールする必要があります。
そのために重要なのがルールを作ることです。
実践例:ルールを決める
私のチームの場合、毎朝、夕の進捗報告を必ず行ってもらうことをルールとしています。
ルールを作ることは、むしろメンバーの行動を縛るように感じるかもしれません。
しかし実際はその逆で、このルールさえ守っていれば、自由に働いて良いという決まりにしておくのです。
この様にすることで、メンバーが裁量を持ちつつも、リーダーはメンバーの進むべき方向をコントロールすることができます。
また、ルールをチーム内で統一することで、メンバーがチームで仕事をしているんだという実感、一体感を持つことができます。
ルールを決めたら、徹底的に守ってもらうことが重要です。
ルールを守ることができなかった場合、なぜ守れなかったのか、対策として何をするか改善策を提出してもらいます。
その改善策が機能しているか、1週間ごとにチェックします。
このチェック作業こそ、ペースメーカーとしての役割となります。
(2)ゴール→現状→プロセスを明確にする
個々の案件の主役はリーダーではなくメンバーです。
メンバー自身が判断、作業して予定通り仕事を終えるのが、リーダーとしての私の理想です。
特に理系のメンバーは自信の技術に自信やこだわりがあったり、自分で進めたいという欲求が強いため、リーダーがあれこれと指示をすることは関係の悪化を招きます。
一方で、こだわりが強いことの弊害として、仕事の方向性が間違っていても突き進んでしまうこともあります。
その対策として、達成すべき目標、現在の立ち位置、ゴールまでの道筋が正しいか互いにチェックすることが効果的です。
この方法であれば、メンバーが間違った方向に進みそうであれば軌道修正できますし、確認ベースの会話ですので、メンバーの自己決定感も損なわれることがありません。
そして毎日、徹底的に行うことも重要です。
日々確認することで、進捗が遅れてたとしてもすぐに軌道修正することができ、案件の炎上を防ぐことができます。
(3)チェックに時間を使う
リーダーがメンバーのペースメーカーとして働くために重要な3つ目のポイントは、チェックに時間を使うことです。
メンバーの進捗が遅いとき、リーダーは指示をしたり、あるいは自分で仕事を引き取って作業したくなるかもしれません。
状況によってはそのような判断が必要な時もあると思いますが、原則は、
「リーダーは仕事を渡したらた信じて最後まで任せる」
です。
仕事は任せるために重要なのが、走っている方向に誤りがないかチェックすることです。
(2)で決めたゴール→現状→プロセスに問題がないか確認することに時間を使います。
実践例:ゴールのチェック
目指している着地点が、リーダーと担当者で違いがないかをチェックする必要があります。
私の職場の場合、以下の3点を必ずチェックします。
ポイント
- 納期
- コスト
- 品質
依頼した仕事のゴールを明確に言語化しておくことで、メンバーが無意味な努力をすることを防いでいます。
実践例:現状のチェック
担当者は現状の進捗、状況を甘く評価しがちです。
- データの解釈に間違いはないか。解釈に他の可能性はないか。そもそもデータに誤りはないか
- 課題設定は適切か。他にも課題はあるのではないか
メンバーとリーダーが「毎日・徹底的に」現状把握することで、認識のずれが小さくなります。
理系リーダーはメンバーの技術的仕事内容にも精通しているはずです。
科学・技術的な面で現状把握にバイアスがかかってないかチェックしましょう。
実践例:プロセスのチェック
案件をスケジュール通り終えるためにプロセスのチェックは重要です。
私は、プロセスのチェックポイントとして3つを重視しています。
ポイント
- そのプロセスで課題を解決できるのか?他の方法はないか?
- スケジュールは適切か?必要な資源は十分か?
- プロセスが計画通りに進んでいるかどうかのチェックはどのように行うか?
メンバーが作った作業計画が、課題解決につながるかを確認しましょう。
もし、より良い方法があるのであれば、担当者自身に考え直してもらうこと必要があります。
スケジュールは予想より遅れることがほとんどです。
リーダーは担当者が提出したスケジュールより、遅くなることを想定する必要があります。
また、必要な物資などの資源が足りているのかを確認することもリーダーの仕事です。
足りていないのであれば、リーダーの責任で確保する必要があります。
何をクリアすればゴールに近づいているといえるのかを確認することも重要です。
- 収率~%以上となれば、この工程はクリア
- 規格Aを工程Bでクリアすれば、ゴールに近づく
など、ゴールまでのチェックポイントをリーダーと担当者の間で明確にしておきましょう。
まとめ
研究開発職リーダーの重要な仕事は、チームメンバーのペースメーカーとして走るべき道をともに作り上げることです。
この記事で紹介した3つのポイントをを実践して以降、メンバーの成果の品質が高まり、スケジュールが後ろ倒しになりにくくなっています。
メーカー若手リーダーの方は是非参考にしてください。